|

Ⅱ 産卵~幼体の確保
マロンの生涯飼育については、1972年に、ペンバートンにあるウエスタン・オーストラリア州南西淡水研究養殖センターで成功している。光量、水温、餌が重要な要素であり、これらがマロンの成熟と産卵に影響する。繁殖の数は種親のサイズに左右されるので、種親には少なくとも2歳、通常は3歳の個体を用いる。マロンは初春に交尾し、メスは200~300個の卵を腹部下の腹肢に付着させ、12~16週間抱卵する。初夏に150~250匹の仔が一人歩きを始める。
繁殖期以外の期間には、小さめの繁殖池(最大500平方メートル)に1平方メートル当たり2匹の密度、雌雄比率1対3で、種親を投入するとともに、十分な餌を与える。(図2参照)
マロンの性別は外見で判断できる。メスは第3胸脚(真中の胸脚)基部に産卵口を有し、オスは第5胸脚(一番後ろの胸脚)基部に性器突起を有する。(モリシー1992年a論文の図を参照)抱卵したばかりのメスには触れないほうか良い。(モリシー1992年a論文)
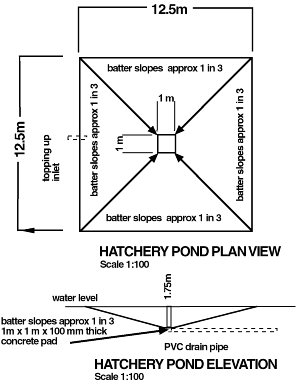 |
|
図 2 |
7月の終わりに、種親を育成池(ストック池)(図3参照)に移す。オスは精胞をメスの第5胸脚の間に付着させる。2.5歳のメスの75パーセントが抱卵するので、抱卵後オスと抱卵しなかったメスを抱卵したメスから引き離す。人工水草を投入して一人歩きを始めた幼体の隠れ場所とし、共食いを防止する。幼体が一人歩きを始めたら直ちにメスの成体を引き離す。(モリシー1992年a論文)
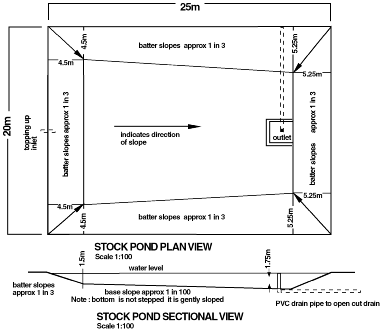 |
| 図 3 |
ウエスタン・オーストラリア州で認可された孵化場では、育成用に生後1~3ヶ月の幼体を販売しているが、多くの養殖業者は自分で幼体を生産している。概して、幼体の確保は、養殖業者にとってもはや大きな制約要因ではなくなっている.しかし、成体槽でどのくらいの数の幼体が残存できるかは、成体槽がマロンに必要な環境にどれほど適応しているかに大きく依存する。
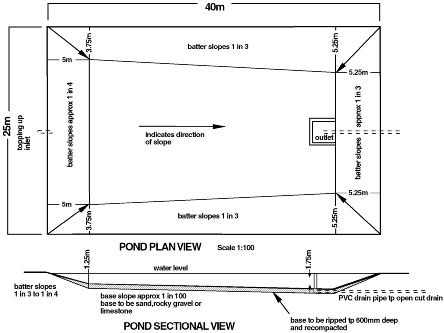 |
|
Figure 4 (click on the figure for a close up
view) |
Page 1 | 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 




